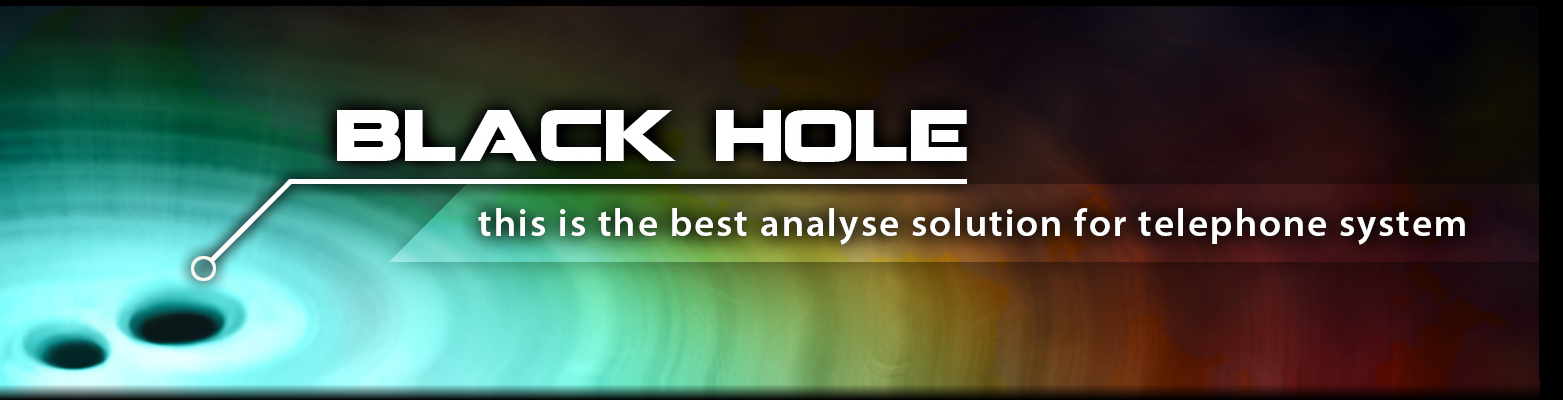「読者に理解されにくいテーマですが、
“こらしめが効かない犯罪者”
について解説をしてみるのはどうでしょう?」
2009年10月10日の岡本さんからのメールである。
日本で検挙される人の約40%が再犯者という。
言い換えれば、その人たちは かつての刑罰が有効でなかったともいえる。
これがこの国の実態である。
では、なぜ有効でなかったのか。
ここで、量刑が適正でなかったのか、それとも刑がその人に合っていないのか?という考えを持つとしたら、それは「矯正」という切り口である。
だが岡本さんが読みたいものは違う。
僕らのような1980年代(第一世代)のハッキング世代は、周囲の誰かが摘発されるごとに、何がマズかったのかをよく研究し、捜査側の手口を学んでいく。
また、チンコロ(密告や捜査協力)した人物をよく観察し、適度な距離を持って、状況によってはそいつを再び利用しようとさえする。
つまり状況に対して「鼻が利く」のである。
ところが受刑するというのは、自分の適量を超えてしまい、発覚して、あまつさえ自分をつきとめられたということである。
しかもその40%が再犯であるということは、40%が前回と同じようなミスをしたということであり、ではなぜそんなミスをしたのか、というところを岡本さんは読みたいのである。
掘って出てくる結論なんて、ロクなものじゃないが、たしかにおもしろいのである。
敗者の弱点をあばくことで、読む人に優越感をもたせるからだ。
「私はそんなバカなことにはならない、だってこうやってセキュリティ技術を勉強しているのだから」
まるで、ゆうきまさみ『機動警察パトレイバー』で内海課長が述べた「週刊誌の作り方」のようだ。
まことにゲスいが、定期刊行物の編集者としては正しい感性である。
正論をふりかざしたところで書籍が売れなければ誰も相手にしてくれない。読者が読みたいものを提供してこそ、商業媒体の編集者といえる。
ただ。それだけに岡本さんは「底辺」の心情を理解していた。
ヤケになった人・ムキになる人・あきらめちゃった人・あきらめられない人…
そういう人たちとの接し方と支え方をよくわかっていた。
だから、あまりに危険な領域には近づかなかったし、やむを得ず そうした人たちのテリトリーに入るときは慎重さを欠かさない人物だった。